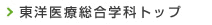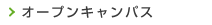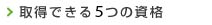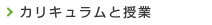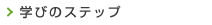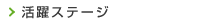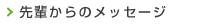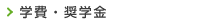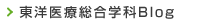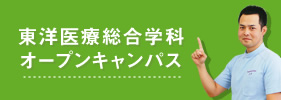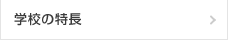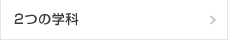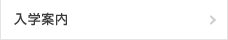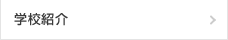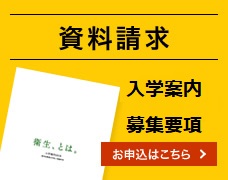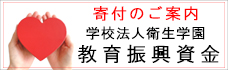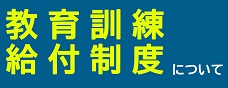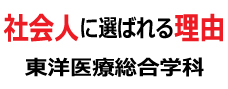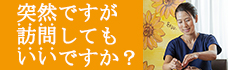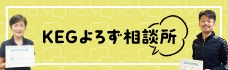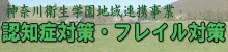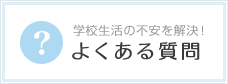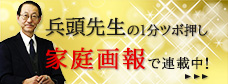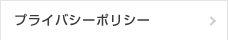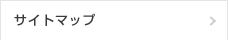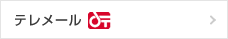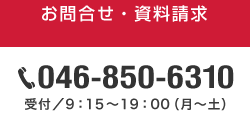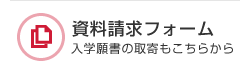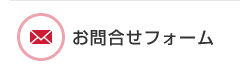トップ 2つの学科 鍼灸マッサージ | 東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【連載企画】スポーツトレーナーとは? vol.4
東洋医療総合学科Blog
【連載企画】スポーツトレーナーとは? vol.4
2020年12月25日
前回、スポーツトレーナーと関わりの深い資格について、法律の観点からその違いについて紹介していきましたが、今回は「スポーツトレーナーの保有資格」についてご紹介しましょう。少し前の研究(中京大学体育研究所紀要 vol.31 2017)ではありますが、プロ野球のトレーナーの方たちが保有している資格に対する調査結果によると、「鍼灸マッサージ師」は12球団すべてに在籍し、人数も最も多かったとあります。
★プロ野球
| 保有資格 | 人数 | 所属チーム数 | 比率 |
| 鍼灸マッサージ師 | 86人 | 12チーム | 57% |
| 日本スポーツ協会公認 アスレティックトレーナー |
23人 | 9チーム | 15% |
| 柔道整復師 | 13人 | 7チーム | 8% |
| 理学療法士 | 10人 | 6チーム | 7% |
| NATA公認ATC | 13人 | 6チーム | 9% |
| その他 | 6人 | - | 4% |
同じく、Jリーグでは「鍼灸師」が最も多く、次は「あん摩マッサージ指圧師」という結果があります。(社会鍼灸学研究 通巻9号 2014)
★Jリーグ
| 保有資格 | 人数 | 比率 |
| 鍼灸師 | 111人 | 62% |
| あん摩マッサージ指圧師 | 78人 | 43% |
| 日本スポーツ協会公認 アスレティックトレーナー |
61人 | 34% |
| 柔道整復師 | 31人 | 17% |
| 理学療法士 | 27人 | 15% |
ここで紹介したのは、どちらも少し前の研究結果ですので、いま現在の状況とは少し異なっているとは思いますが、参考にはなるのではないかと思います。スポーツトレーナーになるには、何かしらの医療系国家資格があった方が良いですが、皆さんがどの資格を取るべきかということは、よく吟味して決めていただきたいと思います。
では、医療系国家資格があればスポーツトレーナーになれるかと言えば、それもなかなか難しいところです。
医療系国家資格の取得を目指す学校では、その資格取得に必要な知識や技術を学んでいきますが、特別なことがない限り、スポーツトレーナーになるための知識や技術は学べません。ただし、スポーツ選手も”ヒト” ですので、その基本となる解剖学や生理学、そして、スポーツ傷害などについては、どの医療系国家資格を目指す場合にも学んでいきます。

スポーツトレーナーを専門職とするには、もう少し深く、その専門性のある知識(例えばスポーツ生理学やスポーツ栄養学など)や技術(例えばテーピングやトレーニング方法など)を学ぶ必要があります。
すでに、大学でアスレティックトレーナーについて学んでいる、とか、パーソナルトレーナーとして働いている、何かしらスポーツに特化した知識や技術を持たれている方であれば、今あるものにそれぞれの資格取得に必要な知識・技術を重ねていけばよいのですが、例えば高校生のように今はまだ何もない方たちは、資格取得の知識・技術に加えて、スポーツトレーナーとしての専門知識・技術も習得しなければなりません。
先に医療系の国家資格を取得する利点は、働きながらスポーツトレーナーとしての学習ができるということです。連載の第1回目で書きましたが、スポーツ系の民間資格だけではなかなかスポーツトレーナーとして働くことは厳しいですが、例えば、鍼灸マッサージ師の資格を先に取得すれば、治療院に就職し、その場でスポーツ選手を診ていきながら自分自身の学習を進めていくことが可能になります。
ちなみに、神奈川衛生学園専門学校では、3年間で「鍼灸マッサージ師」+「日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー」の同時取得を目指すことが可能です。学ばなければならないことは増えてしまいますが、スポーツトレーナーとして働くための学習期間は3年間とグッと短縮することができます。
最後は宣伝になってしまいましたが、スポーツトレーナーとは?という皆さんの疑問の解決に少しでもお役に立つことができましたでしょうか?
これから進路を考えていく皆さんにとって、どの資格を取ればよいのか、どの学校に行けばよいのか、大学なのか専門学校なのか、ということを決めるきっかけになれば幸いです。
広報室